「E=mc²」の式を知らない人はいても、その名前を知らない人はいない──そんな希有な存在が、アルベルト・アインシュタインです。
でも、相対性理論だけが彼のすべてではありません。好奇心に満ちた子ども時代、型破りな学生時代、そして科学者としてだけでなく、平和主義者として世界に訴え続けた姿。
アインシュタインという人物は、知れば知るほど、いわゆる「天才」の枠には収まりきらない深みがあります。今回は、そんなアインシュタインの人生と、彼にまつわるドイツ国内のゆかりの地をたどってみましょう。
アルベルト・アインシュタインとは?
1879年3月14日、南ドイツの町ウルムに、ある普通の家庭の長男として生まれたアルベルト。父は電気機器メーカーを営む技術者でした。
生後すぐに一家はミュンヘンへ移住。少年時代のアインシュタインは、寡黙で内向的、けれど一度興味をもったことにはとことん集中する子どもでした。5歳のときに父から贈られた「方位磁石」に心を奪われたことが、彼の科学への探究心の原点だったとも言われています。
学校では教師の型通りな教育に反発し、決して優等生ではありませんでした。けれど数学と物理においては、すでに教師をしのぐ独自の視点と理解を持っていたのです。
スイスのチューリッヒ工科大学へ進学後も自由な発想で学び、卒業後はスイスの特許局に勤務。ここで執筆した1905年の一連の論文──いわゆる「奇跡の年」の発表が、物理学界を揺るがしました。
理論物理学の革命と、それを超えたアインシュタインの姿勢
アインシュタインの名を世界に知らしめたのは、「特殊相対性理論」と「一般相対性理論」。
「時間は絶対ではない」「光の速度はすべての観測者にとって一定」「重力とは時空のゆがみである」──常識を覆す発想の数々は、当時の物理学に大きな衝撃を与えました。
でも、彼の偉大さは数式や理論にとどまりません。
第一次世界大戦のとき、アインシュタインはドイツの軍国主義に反対し、平和主義の立場を明確に打ち出しました。ユダヤ人として、そして自由な知性の体現者として、ナチスの台頭にも毅然と立ち向かいました。
1933年、ヒトラー政権の成立とともにドイツを離れ、アメリカへ亡命。以後、プリンストン高等研究所で活動しながら、科学の倫理、世界平和、人権問題に至るまで、幅広いテーマで発言を続けました。「科学とは、人類のためのものであるべきだ」と語る彼の信念は、生涯ぶれることがありませんでした。
1955年4月18日、アメリカ・ニュージャージー州プリンストンの病院で、アインシュタインは静かにその生涯を閉じました。死因は腹部大動脈瘤の破裂によるものでしたが、彼は延命処置を望まず、自然のままに死を受け入れることを選びました。
最期の瞬間、彼は何かをドイツ語でつぶやいたといいますが、看護師はその意味を理解できず、その言葉は今も謎のままです。一人の思索者として、静かに、そしてどこまでも彼らしく旅立っていったのでした。
【聖地巡礼】ドイツに残るアインシュタインの足跡
アインシュタインの人生は多くの国をまたぎましたが、彼の原点とも言えるゆかりの地は、今もドイツ国内に点在しています。
▶ ウルム(Ulm):誕生の地
生家は第二次世界大戦で破壊されてしまいましたが、現在はその跡地に記念プレートと小さな展示スペースが設けられています。ウルム市内では、アインシュタインにちなんだイベントやアート作品も見ることができます。
ウルム詳細(外部リンク)
▶ ミュンヘン:少年時代を過ごした街
アインシュタインが通っていたリュイトポルト・ギムナジウムは、現在も教育機関として存在しています。彼が「知的自由のない場所だった」と語ったこの学校ですが、それだけに彼の思想との対比として訪れる価値は十分にあります。
▶ ポツダム:アインシュタイン塔(Einsteinturm)
ベルリン郊外のポツダムには、アインシュタインの理論を実験的に検証するために建てられた「アインシュタイン塔」があります。流線型の近未来的な外観は建築的にもユニークで、訪れるだけでも印象的な体験となるはずです。
アインシュタイン塔詳細(外部リンク)

CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=443359による
名言に触れる:アインシュタインのことば
„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“
想像力は知識よりも大切だ。知識には限界があるからだ。
この有名な言葉は、科学者というより「哲学者」にも近いアインシュタインの内面をよく表しています。彼にとって科学とは、すでにある知識を整理するものではなく、世界に対する「問い」を立て直す作業でした。
私たちが日々の生活の中で「どうせ無理」と思ってしまう場面でも、ほんの少しの想像力が、新しい視点を開いてくれるのかもしれません。
さいごに
アインシュタインというと、白い髪の風変わりなおじいさん──そんなイメージで語ってしまいがちですが、実はとても情熱的で、繊細な感性をもった人物だったんですね。
彼の生きた時代は、科学の発展とともに、戦争や差別、亡命といった苦難も重なっていました。それでも、問いかけること、考え続けることをやめなかった彼の姿勢には、今の時代だからこそ学ぶべきことがあるように思います。
次にベルリンやポツダムを旅する機会があれば、少し足をのばしてアインシュタイン塔を訪れてみてはいかがでしょう?幾何学的なその建築の中に、彼の「問い」が今も響いている気がします。

問い続ける心が、いちばんの才能なのかもしれませんね

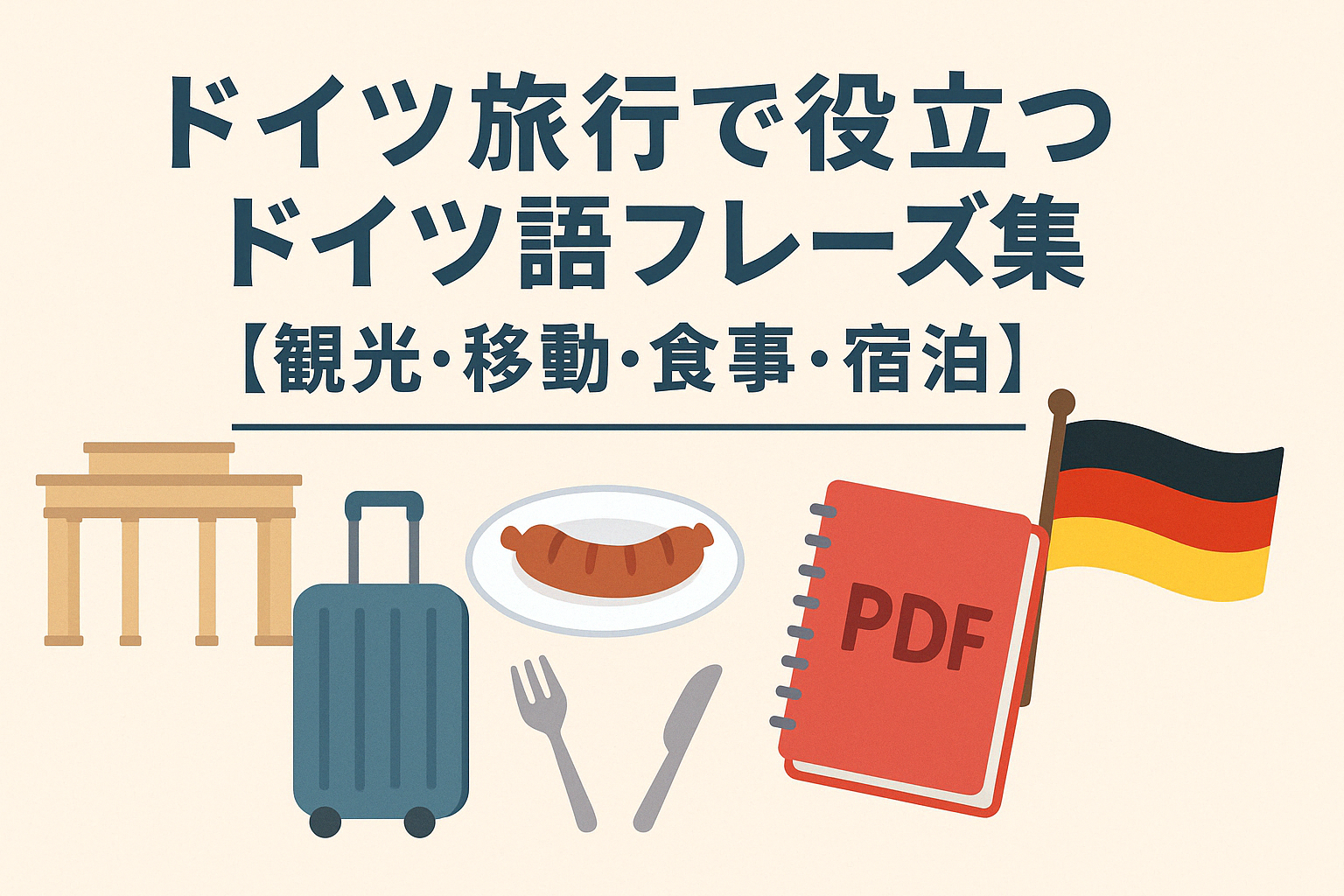
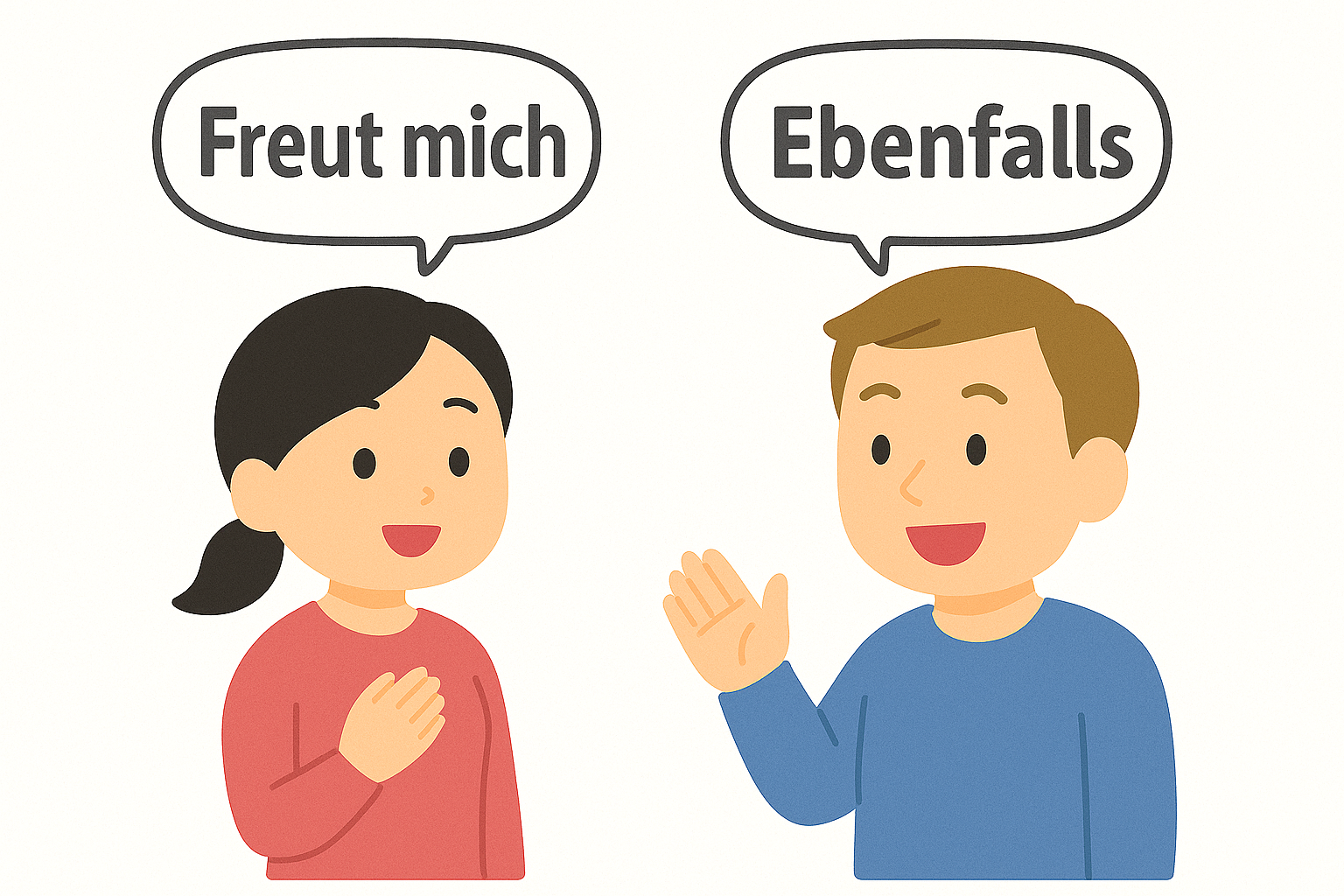













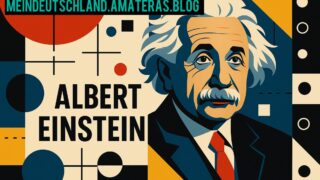

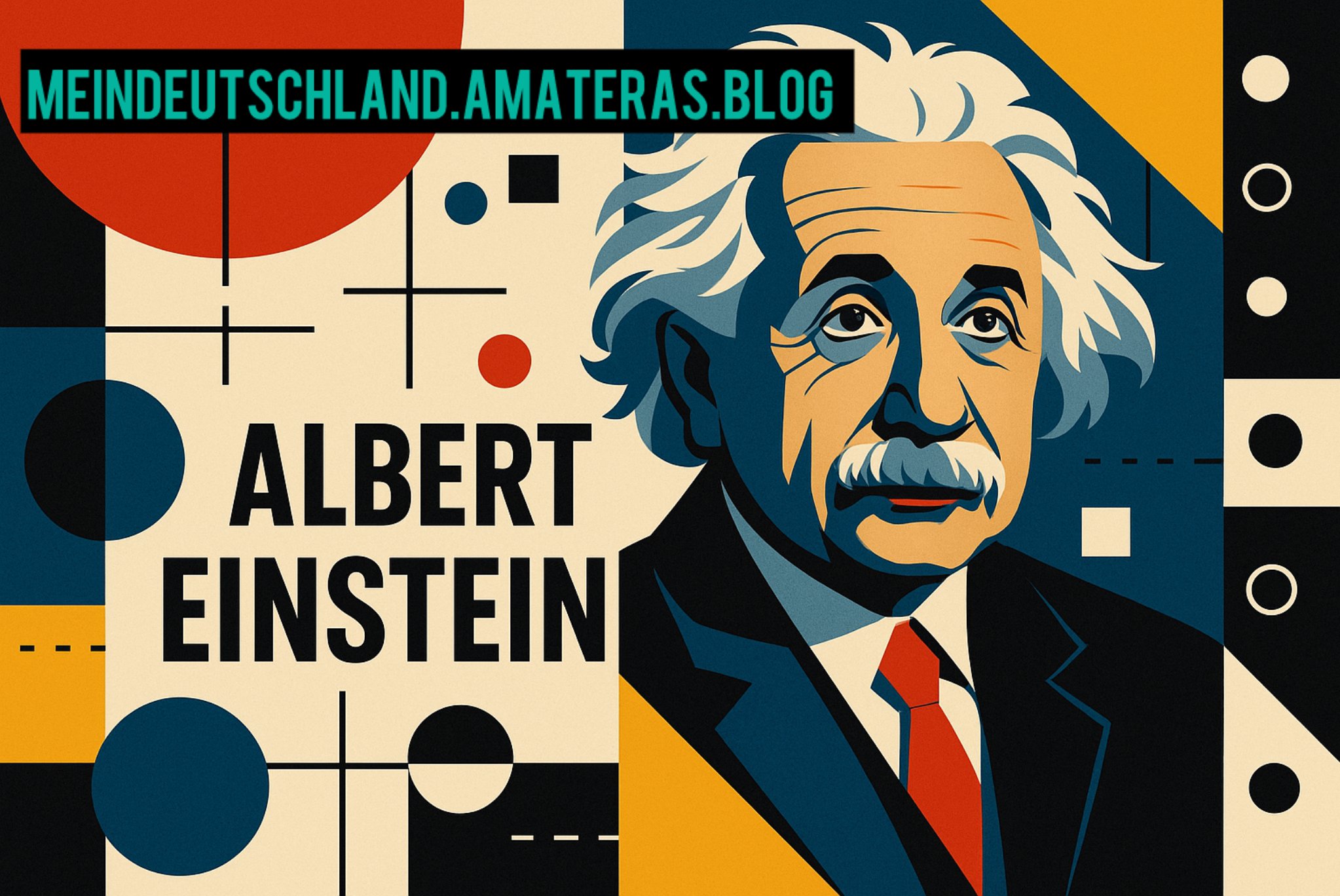





コメント